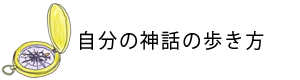こんにちは冨永のむ子です。
今日はオンラインサロンのMTGがありました。
ジャッジしてしまって苦しい、という方の話をうけて、夫がこんなことを言いました。
ジャッジするのは全然いいと僕は思っていて。
でもその後に、思いこみで固まっていく、
その人はこうこういう人だから悪い人だとか・・・、その相手を変えようとするとか・・・・
「ジャッジしてはいけない」の誤解
自己啓発の世界で、ジャッジをやめる、といいますよね。
私も講座でお伝えすることがあります。
でも言葉って難しいね。
「一切の判断を手放さなければいけない」 と思ってしまう方もいる。
「あの人はこういう人だな」とか、「この人とは合わないかも」と感じることすらダメだと思って、自分の自然な感覚まで否定してしまう。
でも、それは不自然じゃないかなと。
そうでなくて、そのジャッジが自分や周囲を苦しめるなら手放した方がいいよね、ということ。
夫がそのへんをわかりやすく話してくれたので、
その話を要約しつつ頭の中を整理しつつシェアします。
ジャッジそのものが悪いことではない。
「この人はどういう人なんだろう?」
「ああ、こういうタイプの人なんだな」
こう想像してみることもジャッジ。
これは観察であり、理解しようとする行為です。
これは人に対する興味があるからこそできること。
実際に話してみて、自分の見立てと比べた時、
「やっぱりそうだった」
「あれ?思ってたのと違った」 と気づきを得ていく。
これは、人間関係を築く上で むしろ必要なプロセスです。
ジャッジからの思いこみが自分を苦しめる
一方で、自分を苦しめるのはそのジャッジから相手を決めつけて、思い込みで固めてしまうこと。
「この人はこういう人だから、悪い人だ」?
「あの人はああいう人だから間違っている」
そう決めつけて、思い込んで?相手を変えようとしたり、 壁を作ったり、拒絶してしまう。
こうなると、人間関係がギクシャクして、結局、自分が苦しくなります。
「ジャッジしない」の真意は、「決めつけて凝り固まらない方が楽だよ」 ということかなと。
「一切の判断をするな」「何も感じるな」 という意味ではありません。
「この人はどんな人だろう?」と興味を持ち、
「こういうタイプかな?」と仮説を持つのは自然なこと
そこから先、 実際に接してみて、
「やっぱりそうだった」「あれ?違った」と柔軟に修正をいれる。
これは、健全な人間関係に むしろ必要なことなんだし、
その仮説が当たっていたとしても、人は変わるから、
永遠にずっとその人がその仮説の通りとは限りません。
大切なのは「その後」
柔軟に対応できる場合は、実際に話してみて、
「あれ?思ってたのと違うな」と気づいたら、?
認識を更新できる。
「苦手なタイプだと思ったけど、 話してみたら意外と気が合う」
ということもあるでしょう。
これは自分を苦しめません。
ギャップ萌えもあるかもしれないしー。
凝り固まってしまう場合一方で、一度下した判断を絶対視するとしんどいし泥沼。
「この人はこういう人だ」と線を引き
相手を変えようとしたり、変わらないと、壁を作ったり、被害者意識を持ったりするとね。
でも覚えておいた方がいいのは、人は変えられないということ。
(自分のことだって変えることは難しいのに)
それなのに相手を変えようとするから、
イライラしたり、相手を責めたり、そんな自分を責めてしまう。
いいこと一個もないですね。
ジャッジしていることに気づくだけでいい。
じゃあ、どうすればいいか・・・
ものごとはシンプル「ああ、今ジャッジしてるな」と気づくだけでいい
「ジャッジしてる自分はダメだ」 と自分を責める必要はありません。
これは、自分はダメな人間だという思いみに走るだけだから
そうではなく、
「ああ、今、決めつけそうになってるな」?
「思い込みで固めそうになってるな」
そう気づいて、一歩引いて眺めて、心を柔軟に保っておく。
それだけでいいのです。
ジャッジすること自体に良い悪いはありません。
人間だから ジャッジしてしまうのは当たり前。
一切の判断を手放す必要はありません。
人を観察し推測しすることは、自然なこと。
ただし、
・ 思い込みで固めないこと
・ 相手を変えようとしないこと
・ 心を柔軟に保つこと
それが、自分も相手も心地よい関係でいるコツかな。

人をジャッジをして優劣をつけたり、
損得や善悪から相手をコントロールしようとすると、
自分も周囲も心地悪くなり、よき流れには乗れませんよね。
これは思考判断を制御している第6チャクラのテーマ。
第6チャクラが整うと、
自分や周囲を苦しめる厳しいものだった思考判断が
より柔軟に色んな意味で「適当」なっていきます。
その結果、自分も周囲の関係性や、
業務上のコミュニケーションなどが自然にスムーズになりますね。
自分の中で起こる感情や思考の適切な扱い方に興味が湧いた方は、こちらへどうぞ。
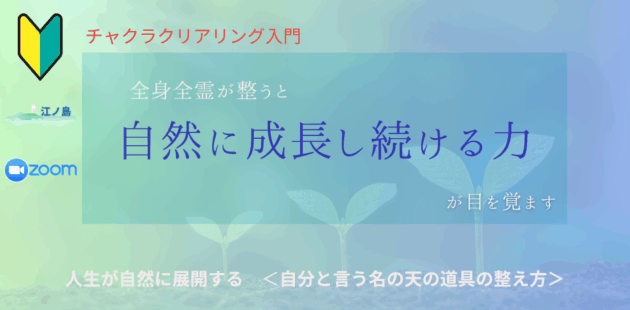
それでは今日はこのへんで
お読みくださってありがとうございます。
感謝をこめて 冨永のむ子
自分の神話の歩き方 無料メールマガジンバックナンバーより抜粋
【自分の神話の歩き方】無料メールマガジン登録はこちら
■提案者
冨永のむ子 自分の神話ナビゲーター
株式会社パーソナルクレド舎 COO
自分の神話:大切なことを犠牲にせずに、本当にやりたいことをして生きていく人生のこと
早稲田大学法学部卒 株式会社リクルートで広告ディレクターとしてIT業界や金融業界の業界最大手企業を担当。徹夜で身を粉にして働く中「自分にしかできないことをしたい」と起業のために退職。
妊娠、生まれた息子の病気、産後鬱の中で、それでも起業しようともがき続ける中、腕の中にいた赤ん坊の息子から「ママ幸せ?」と言われ生き方、働き方を見直す。
その過程で自分のガイドとなるシンボルと、人生のシナリオが降りてくることで迷い道から抜け出し人生が前に進むように。
シンボルとシナリオの仕組みを【パーソナルクレド®】と名付け、使命に目覚めるサポートを開始
2011年 夫婦で株式会社パーソナルクレド舎を設立 自分の神話塾 起業塾を主宰
【パーソナルクレド®を活用した生き方・働き方の変化事例】
パートの事務員の主婦が、法律に目覚め司法書士へ転身
絵心の全くなかったアパレル販売員が、絵を描くことに目覚め売れっ子アーティストへ
PCもSNSも使えなかった主婦たちがWEBを駆使して天命の事業を立ち上げる
といった、平凡に暮らしていた人たちが未知の可能性を開花させていく一方で、
・国連職員・パリコレモデル・音楽プロデューサー・弁護士・ニュースキャスター
・医師・ミュージシャン・書家・ジュエリーデザイナーなど、それぞれの領域の専門家が、肩書や資格の枠を超えて、自分が気づいていなかった、本当に望んだ独自の生き方・働き方に目覚めています。
拠点は生まれ育った湘南、江の島の中の江島神社の参道脇にサロンをかまえる
プライベートは二人の男子の母

シンボルは大地
2007年に自動書記で出てきたパーソナルクレド®に
【生きる意味を見出す手助け】
と記されていました。